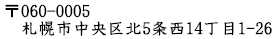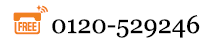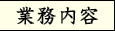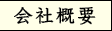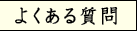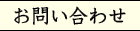|
|---|
 |
|---|
|
| 「家紋は、その家の名字のようなもの。何万種類もあって、今だに初めて見る物もある」という須藤さん |
 |
|---|
キュッキュー。
布と糸がこすれる音がリズミカルに響く |
|
それぞれの家によって何千、何万種類もある家紋。これを着物に付ける職人がいます。
刺繍のように縫いつける方法と、染めたり描いたりしてつける方法の2通りがありますが、須藤洋子さんが縫う方の"縫い紋"の職人になったのは20年以上前のこと。
「須藤紋章店に嫁ぎ、自然に修業を始めることになりました。」
経験豊富な男性の下について、毎日毎日何時間も座りっぱなし。
はじめは思ったように出来上がらず、その日の体調によっても縫い目の大きさが違ってきたりと、「ずいぶん難しいものだ」と感じました。
お客さんの紋を縫えるようになるまで2〜3年かかりましたが、独り立ちしてからも、1度もこの仕事をつらいと思ったことはありません。「自分の刺した着物に、思わぬところで出会ったりします。自分の手がけたものはひと目で分かりますからね。ああ、着てくれているなと嬉しくなり、自分が作ったものがずっと残っていくという喜びを感じます。」

着物を着ない人たちが増えてきました。加えて、若い世代になると、自分の家の家紋がわからないという人たちも少なくありません。この分だと、だんだん注文が減って...ふと不安がよぎり、ひと縫いひと縫いする度に、もっと着物を着てほしいという願いがこもってしまいます。「夏の浴衣なら気軽に着られますよね。お盆だけじゃなくって、夏の外出にももっと。」

|